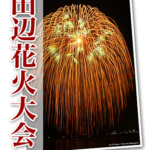もういくつねると お正月♪
お正月には 凧(たこ)あげて♪
こまをまわして 遊びましょう♪
はやく来い来い お正月♪
もういくつねると お正月♪
お正月には まりついて♪
おいばねついて 遊びましょう♪
はやく来い来い お正月♪
ご存知、瀧廉太郎作曲による日本の唱歌ですね。
一番は男の子の正月遊び、二番は女の子の正月遊びですね。
ちなみに、二番の歌詞の中に出てくる「おいばね」というのは、「羽根つき」のことです。
お正月というのは、特別な日ですね。
去年一年間が無事であったことと新年を祝うために、正月飾りをして、行事や御節(おせち)料理を食べてお祝いします。
大人も子供も、「一年で一番大事な日」と感じている人が多いのではないでしょうか。
今回は、お正月にする飾り付けについて見てみましょう。
お正月飾りの名前
お正月飾りというのは、もちろん、正月を迎えるにあたり飾られる物です。
でも、地域の特性もあり、日本全国の正月飾りを挙げると膨大な量になります。
ここでは、よく耳にするお正月飾りをざっと挙げてみます。
・注連縄(しめなわ)
・鏡餅
・玉飾り
・餅花(もちばな)
・輪じめ
・床の間飾り
・神棚飾り
・羽子板
・破魔弓・矢
どれも耳にしたことぐらいはあるのではないでしょうか。
お正月飾りの意味
それでは、お正月飾りの意味合いを見てみましょう。
門松(かどまつ)

常盤木(ときわぎ)には、神様が宿ると思われてきました。
常盤木というには、常緑広葉樹林のことです。
この中でも、松は、生命力や不老長寿、繁栄の象徴とされていて、おめでたい樹として、正月に飾る習慣があります。
現代の門松は、竹が目立ちますが、その中心は松なのです。
注連縄(しめなわ)

神社では、神域と現世を隔てる結界の役割を持ちます。
また、日本の正月には、家々の門や玄関といった出入り口に飾ることで、厄や禍を祓う結界となると言われています。
そうそう、相撲の最高位である横綱が締めることが出来る「横綱」も注連縄なのです。
鏡餅

穀物の神へのお供え物として餅を飾ります。
鏡の形に似ていることからついた名称だと言われています。
玉飾り

注連縄を輪にしたものに、前垂れ、裏白、紙垂、譲り葉、橙、海老、扇など色々な縁起物をつけたしめ飾りです。
玄関先や神棚の下に飾ります。
餅花(もちばな)

一部地域で、ヌルデやエノキ、ヤナギなどの木に、小さく切った餅や団子をさして飾るもの。
一年の五穀豊穣を祈願する意味があると言われています。
輪じめ
注連飾りを簡略化したものです。
部屋やキッチン、トイレなどの水まわりに飾ります。
床の間飾り
そもそも、床の間は、書画や置物を飾ることを目的とするものでした。
その後、有力者に仕える者が主人を迎え入れるために、客間を飾り付ける一部として床の間が作られるようになりました。
現代では、住宅事情から床の間は減っていますね。
床の間の一般的な飾り方としては、掛け軸、生け花、置物を飾ります。
神棚飾り
神棚がある家では、正月を迎えるにあたり、神棚を飾ることが大切な行事になります。
神棚は、扉が一枚の「一社造り」と三枚の「三社造り」が普及しています。
事前に神社でお受けしておいた、お札を納めることになります。
お供え物としては、中央にお米、向かって右にお塩、左にお水です。
羽子板

もともとは、羽根突きの道具として用いられていました。
徐々に厄払いとしても使われるようになってきました。
そして、魔除けとして正月に女性にあげる習慣も出来てきたようです。
破魔弓・矢
もともとは、お正月の男の子の遊び道具として用いられていました。
江戸時代以降、男の子の成長の無事を祈る縁起物として、装飾した弓と矢が、初正月に贈られるようになりました。
その後、矢だけが魔除けとしてお正月に神社で授けられるようになっています。
お正月飾り処分の仕方
それでは、お正月飾りの処分の仕方を見てみましょう。
門松の設置は、12月13日以降ならばいつでも良いとされています。
しかし、30日や31日では、ギリギリ過ぎて、神をおろそかにするということで避けられます。
また、29日は、「二重苦」などといって避けられるようです。
門松を飾る期間のことを松の内といい、本来は元日から1月15日までを指していましたが、近年では7日までとするのが普通です。
門松は、1月15日に行われる火祭り「左義長(さぎちょう)」で処分してもらいます。
左義長は、どんと焼きとかお焚き上げ、焼納(しょうのう)とも言われています。
門松と同様の取り扱いです。
神仏に感謝し、無病息災などを祈って餅を頂く儀式「鏡開き(かがみびらき)」によって食されます。
鏡開きは、松の内が1月7日の地方では11日に、1月15日の地方では20日に行われます。
門松と同様の取り扱いです。
門松と同様の取り扱いです。
門松と同様の取り扱いです。
松の内が終われば、片付けます。
処分が必要なものは、左義長で処分してもらいます。
松の内が終われば、片付けます。
処分が必要なものは、左義長で処分してもらいます。
羽子板は、女子の元服(結婚と同時、あるいは未婚でも18歳から20歳くらい)まで置いておくものとされています。
羽子板は、左義長で処分してもらいます。
破魔矢だけでなく、お守りやお札も、効果は一年間と言われていますので、左義長で処分してもらいます。
破魔弓を処分する場合も同様です。
破魔弓は、男子の元服(数え年で12歳から16歳)まで置いておくものとされています。
まとめ
日本に昔から伝わる儀式や慣習が、現代では、どんどん簡略化されたり忘れ去られたりしています。
何か寂しい感じがしますが、これも時代の流れですね。
「一年の計は元旦にあり」
いろんな意味で、リセットすることができるのがお正月だと思います。
思わしくない一年を過ごしたとしても、新しい年を迎え、心機一転頑張って行こうというきっかけ。
日本人は、それをお正月に再認識することが出来ると思うのです。
その手助けをしてくれるのが、古来よりの儀式や慣習です。
大事にしたいものですね。